




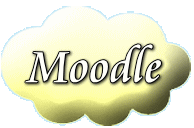


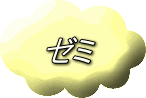
SLA評価研究会 (SLAA :Second Language Acquistion & Assessment Research Group) の紹介ページです。
     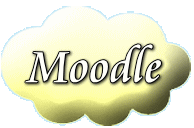   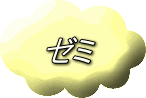 |
|||
|
Teaching
ESL/EFL listening and speaking
2011/05/26
Chapter 1 Parts and goals of a listening and speaking course
1.
4つの要素The Four strands
n
良い授業とは、「意味重視のインプット」、「意味重視のアウトプット」、「言語重視の学習」、「流暢さの向上」 の4つの要素の釣り合いがとれている。
n
タスクに時間をかけるだけ向上する原理(time-on-task principle)、4技能の重要性を重視。
2.
「意味重視のインプット」:リスニングとリーディングからの学習
n
条件:内容は既に馴染みがある、言語についてほぼ理解できる。未知語は文脈から理解できる、インプットの量が多い。
ex)多読、物語を聞く、TVを見る、会話で聞き手となる
n
研究:多聴、graded-readerでの多読から語彙習得、各技能向上がみられた。
n
偶発的学習は、繰り返されるインプットの量が十分でなければならない。
3.
「意味重視のアウトプット」:スピーキングとライティングからの学習
ex)会話で話す、スピーチをする、手紙を書く、物語を話すetc
n
条件:馴染みのあることについて書く・話す、情報を伝えることが目的、用いる殆どの語彙について熟知している、コミュニケーション方略、辞書などを用いることができる、発話する機会が十分
n
Swainのアウトプット仮説(1985):
アウトプットの3つの機能
①
気付き/きっかけの機能
・アウトプットの気付きはインプットの気付きよりも効果的
・気付きの機能は、学習者が、気づいた欠落を埋めることで完了する
②
仮説を試す機能
コミュニケーション成立がみられたか、フィードバックを基に確認または修正
③
メタ言語機能
strip story dictoglossなどグループワークで特に言語について話し合う
追加④:generative use: 学習者が使用したことのない言語項目を使う。(対話の順番、話し方など)
4.
「言語重視の学習」
ex)発音練習、単語カード、翻訳
n
条件:言語特徴に注目、同じ特性が頻出し、何度も注目できる。
n
短時間で多く学習できる、意図的学習によって、文法、複数の語のまとまりを効果的に学習できる。
5.
リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングで「流暢になる」
n
意味重視の活動で知識を応用する。
ex)速読、スキミング、繰り返しの再輪、簡単な物語のリスニング
n
条件:内容になじみがあり、意味の受容、伝達が中心。普段よりも速い速度で行う。多量のインプットアウトプット
n
2つの活動タイプ:同じマテリアルを繰り返すもの(4/3/2)と繰り返さないもの(多読)
6.
4要素の釣り合い
n
教師は2週~1カ月の間の学習を分類化することで、学習者が4要素の活動をバランス良く行っているかを評価できる。
4要素の均等化の根拠
n
Ellis(2005): 指導は、主に意味重視であるべきだが、言語(form)も重要である。
n
言語重視は、語彙習得など特定の項目に効果的であるが、効率さでは劣っていても、効果がより広域にわたる、意味重視の活動との釣り合いが大切である。
n
熟達度により、4要素の配分が変わる指摘もあるが、必ずしもそうではない。
7.
4要素の統合
短期集中講座や、内容重視の学習であるか、など学習形式の違いによって、4要素の必要性は異なり、教師、生徒、学校によっても4要素の比重の置き方は異なる。
8. 4要素を考慮した教育指針
ü
リスニングとリーディングから理解できるインプットを多く提供し、意図的に学習を促進させるようにする。
ü
様々な形式によって、話し・筆記のアウトプットをさせるのを助けて、共同学習の機会を与える
ü
語彙・文法など言語項目を学ぶのを助け、学習の方略指導をする。
ü
各4技能の流暢さを促進させる活動を行う。
ü
4要素の均等がとれるようにする。
ü
役立つ言語項目を繰り返し扱う。
ü
学習者の必要性に応えるために分析、モニター、測定を行う。
n
ドリル、発音練習など古典的手法も適度な焦点・時間の当て方によって4要素のひとつとなる。
9. 学習目標
n
LIST:言語項目・内容・技能・談話構造 (p. 15 Table 1.1 参照)
n
授業構成に重要な点
1.
様々な言語的特徴に触れるために、多様な談話形式に触れるべき
2.
各談話形式は異なった言語形式を持つ。「くだけた会話ができる=形式ばった会話ができる」ではない。
3.
不慣れな談話形式の場において、学習者は自らの言語能力に気づく。
2011/6/16
Chapter 4. Language-focused Learning through Dictation and Related activities
1. Introduction
n Dictation
△伝統的な指導方法 △指導よりはテストのため
・価値のある指導法・・・言語学習-句,節レベルの形式に焦点を当てられる
-理解面の正確さについてのフィードバックが与えられる
・意識させる
・関連する活動 ◎dictogloss ◎running dictation
n 教材は,学習者のレベルに合わせて選択できる。
・方法 ①教師が全文を読む
②3-7語の語のまとまり毎にポーズをおいて読む
③学習者は書きとる。
④教師は一文ずつ読む。
⑤正確に書けたか確かめる
・○ 学習者自身が何を間違えたかがわかる
n 単語の意味はわかるが,なじみのなないコロケーションや構文についてディクテーションを行うことが最も効果的
n 自己採点や座席の近い人と採点を行うことで教師の労力は少なくなる。
2. Choosing Dictation text
n 教材については,既習,未習,同等レベルで他の教材などが使えるが,未習の語は含まれるべきではない。ユーモアのあるもの,ありきたりでない話,会話,詩などがふさわしい。
3. Pre-dictation Exercise
n Exerciseを行ってからdictationを行うことにより,構文(構造)に注目できる。
n Exercise 例
1. 書きとる前に,教師が全文を読む → 全体像が把握できる。
2. 既に渡されて読んである → 動詞の形,複数形,発音の練習になる
3. 黒板に教師が書いたものを学習者が修正する → 冠詞 (a, the),名詞の複数形,動詞 (~ing, -s, -ed)
4. 学習者に聞き取りのポイントを指示
5. 教師が黒板に右のように単語を書き,生徒は聞こえた単語をA,Bで答える。
6. 教師は何回かテキストを読んで生徒の質問に答える。
7. はじめに質問が与えられ,それに答える。
4. Variation of Dictation
n Running Dictation
1. ペア,または小グループで活動
2. 一人が書き手,残りの生徒はrunner(廊下などに貼り出されたtextを見てグループに伝える)。
3. リレー形式でrunnerが戻ってきたら次の生徒が伝える役目になる。
4. リスニングやスピーキングの活動としたい場合は,掲示されたものを使うのではなく,教師が声を出して読み,runnerに伝える方法も可能。
5. 文を書くのではなく,絵を描くこともできる。
<コメント> ・騒々しくなりマネージメントが難しくなることも考えられる。
n One Chance Dictation
生徒を集中させるため,何度も教師が英文を言うのではなく,一回のみ読むようにする。(生徒の間違いが少ないのなら可能)
n Dictation of Long Phrases
書く活動を行う時,短い句を1回読むのではなく,10語以上の長い句や文を何回か読む。
n Guided Dictation
名詞,動詞,形容詞,副詞のいくつかをTextの中に出てくる順番にあらかじめ黒板に書いておく。そして,学習者は他の難しい語に注目できるようにする。指導者は,1回(必要があれば数回)英文を読む。
n Dictation for a Mixed Class
学習者の習熟度がばらばらの時に活用。
①ポーズを入れずに通読。
②高い習熟度の学習者のために(句ごとに)速く読む。
③その他の学習者のためにゆっくりと読む。(高い習熟度の生徒は,ここで確かめができる)
n Peer Dictation
Dictationを行う英文を学習者が持ち,小グループで活動を行う。
例)「競争」の形式をとることもできる。
①ペアで活動,一人が読み手でもう一人が書き手になる。
②クラスで一番早く終わったペアが “Stop!”というとクラス全体の活動が終了する。
*書き手は,読み手に繰り返すことや語の綴りを聞くことができる。
n Completion Dictation
①学習者に,書きとらせる用紙を数種類あらかじめ配布しておく。
その用紙は空所があいていて,一枚目よりも2枚目,3枚目の方が空所が多くなっているようにしておく。
②指導者が句ごとに読む英文を聞きとって書く。
*学習者が書き終えた用紙は,2枚目の時に見えないように折っておく。
n Perfect Dictation
・Dictationの採点し生徒に返却した後にもう一度同じ英文のdictationを行う。
・3回目までには,学習者は完全に書けるようになる。
*1回目の採点は,指導や学習者が完璧に学習するまでの最初の一歩である。
n Sentence Dictation (Tucker, 1982)
教師が言った複数の文を学習者が書き取るとき,次の英文が読まれる前に,正解を一文ずつ与えていく方法。こうすることで,学習者は間違いを知ることができる。
n Unexpected Dictation
教師が通常の話すスピードでテキストを録音しておく。Dictationにおいて普通とられるポーズなしに録音するようにする。生徒はそれぞれ録音したものを聞きながらスクリプトを完成させていく。ピッチを変えずに速さを遅くすることができる安価なソフトウェアもある。
5. Related Techniques
1) Delayed repetition
学習者は長い句を聞いて,数秒後にそれを繰り返す。この方法は言語の習熟度テストとして用いられてき た方法であるが,授業でも用いることができる。一度に言うのを3語くらいからはじめ,語数を多くしていくことや,ポーズを長くしていくこともできる。
2) Read-and-look-up
Dictation の良い練習になる。
①ペアになる(話し手と聞き手)
②話し手がテキストの句を見て覚え,テキストを見ずに話し手に向かって言う。
*読んでいるときは声に出さずに,短時間で覚える。
*教師がテキストを句に分けてもいいし,生徒自身で分けてもいい。
*家で鏡の前で練習する方法もある。
West(1960)によると・・・ < 本 → 脳 → 口 > というつながりをたどる。
3) Delayed copying
リスニングやスピーキングを含まないdictationに関連した活動。
テキストの文をできるだけ長く覚えてそれを書く。一語ずつ書くのではなく,句を覚えてテキストから目を離して書く活動。Dictationとは異なり,個人的な練習に向いている。
4) その他
単語(content words)を与えておくことにより,長い句でも容易に記憶に留めることができる。
6. Monitoring Dictation
n 教師は,生徒が短期記憶に留めておける単語の数に注意を払うとよい。以下はLado (1965)による研究結果
1) 母語よりも外国語の方がmemory span が短い。
2) 言語の習熟とともにmemory spanは増える。
3) 母語と外国語の発音面や文法面の違いが大きいほどmemory spanについての差も大きい。
4) 数よりも文脈的な事柄の方がmemory spanとの関係が大きい。
n 文の難解さは,その長さと統語的な複雑さによって決まる。また,統語的な複雑さは従属節の有無による(Harris, 1970)という研究や人によってworking memoryのサイズが異なる,という研究結果がある。
7. Dictogloss and Related Activities
n Dictogloss の方法
1) 準備:語彙,トピックについて・グループを作る
2) 教師が普通のスピードで話す英語を一度(メモを取らないで)聞く
3) 教師が普通のスピードで話す英語をもう一度聞く。学習者は重要だと思われる語をメモする。
4) メモをもとに話の概要を再構築する。グループで活動する。
5) 教師は,黒板やOHP(OHT)などを用いながら比較検討し,間違いは正す。
n Dictoglossは,文の意味や内容に焦点を置いた活動であるが4), 5)では形式(語形,語順,語の綴り,文法)に注目できる活動だが,それらに留意しない場合もある。
Wilson(2003)は,以下の“Discovery step”を設けることを提案している。
① どのような問題があったか
a) 音が聞き取れなかった。 b) つながって聞こえる音を単語に分けることができなかった。
c) 音は聞こえたが,その意味が浮かばなかった。 d) 知らない単語だった
e) 単語はわかったが文の一部分の意味がわからなかった。 f) その他
② ①のstepを通して学習者が学ぶこと
1) 語のつながり 2) 既知語が文の中やなじみのないコロケーションの中でどのように発音されるか
3) そこで使われている文法や語に慣れる 4) top-down の効果
n Dicto-comp:Dictation+composition
Dictoglossとよく似た活動で,グループにならずに個人で活動を行う。準備次第で学習者の認知の負荷を少なくすることができる。
n Related Technique
1) Retelling
違う話,もしくは一つの話をいくつかのパートに分けて,その内容について説明をする活動。
<M高校での授業実践の例>
①36人の生徒について,くじ引きで3人グループを作りながら入室(A教室)。
②本時の授業についての説明。(A教室)
③3人の指導者の下,3教室に分かれそれぞれ違う英文を読解しリテリングの練習をする。(A・B・C教室)
④A教室の3人グループに戻り,それぞれが学習した内容についてリテリングを行う。(A教室)
⑤授業のまとめ
Ø 4/3/2 techniqueの使用もできる。
Ø 4技能の融合 (Elkins et al. 1972)を参考に,同じ情報(text)についてretelling, dicto-compを繰り返す方法
2) Reproduction exercise
学習者がテキストを読んだ後に,それを読み返さずにその内容について書く活動。表を完成させるような活動を入れるとよい。
3) Oral Reproduction
①教師が「一度だけ a dialogueをいう」と生徒に伝える。
②教師はdialogueをいう。
③生徒は何も見ずに一番初めの文,もしくは一番初めの語を繰り返す。
④生徒が言ったことが正しかったら次について尋ねる。
⑤全部できるまで繰り返す。
*生徒が難しい様子だったら声に出さずに,それを発音する方法もある。
*この方法は,人数の多いクラスに向いているだろう(???)
*詩や歌を利用する。
4) Disappearing text
①教師は,50-60語(生徒の能力に合わせて語数は調節する)の文を黒板に書く。
②1~2人の生徒にそれを音読するよう指示する。
③教師は,いくつかの単語(始めはa, the, in, of, I, he など)を消す。
④他の生徒に音読するように指示。
⑤黒板に単語がなくなるまで繰り返す。
*何回も繰り返すので覚えてしまう。初級者向きの活動
5) Phrase by phrase
教師がPhrase ごとに読んだものを生徒が繰り返していう活動であるが,教師が発音した後に少し時間を置くことによって(5秒程度)記憶に長く留めておくことになる。
n Dictationをもとにしたdictoglossなどの活動は,教材の難しさは別にして学習者の習熟度に合わせることができる。
・英文を繰り返す回数,速さ
・inputとoutputとしての産出(production)の間の時間差
・outputに求められる詳しさ
n これまでに延べてきたことは,語学の学習でありさらには技能の習得(skill learning)でもある。技能の習得については,音のつながりのようにbottom-upの面と推測を行う等のtop-downの面とを併せ持つ。
Chapter 2 Beginning to Listen and Speak in
Another Language (pp.17-35)
リスニング・スピーキング初級コースの目的:
①
できる限り早く意味重視のインプットとアウトプットを可能にする
②
リスニングとスピーキングで成功することで動機づける
③
必要性に応じた学習をさせる
1.
What
should they learn?
n
初級者クラスは、学習者の年齢、学習目的、EFL/ESLなどによって、内容が異なる。
n
成人した移民で、英語圏で生活するにあたって、日常英語が必要な初級者の生徒に必要な学習項目
①
アルファベット:筆記練習、音韻知識
②
自己紹介の文章
③
日常生活での語句
④
視覚語彙:標識、券、ラベル
⑤
教室内での表現:Excuse me, How do I say this? …etc
⑥
頻出語句:数字、教室内の物、色、日時etc
n
大人:旅行するための語句:survival vocabulary 120の語句(Appendix 1, p.179~)
n
子供:頻出語を学ぶことによって、簡単な文章を読み、活動ができるようになる。
n
生徒の必要性に応じた内容を取り入れることによって、生徒は達成感を持つことができる。
2.
How
should the teaching and learning be done?
初級学習者のための5つの原則:
Meaning, Interest, New language, Understanding, Stress-free (MINUS)
①有意義で関連性のある内容
n
文法説明よりも、学習者が目的に応じてすぐに使える内容。(例:p.19)
書かれた文章を提示することによって、見ずに話し、他人の会話を聞きとることができる。また、文字と音声を結び付けることができる。
n
教師・生徒間での意味重視の会話:授業運営、情報の会話、前時の内容確認、活動に対する生徒の意見を聞く。
②興味を引く多様な活動
短く、多様で、生徒が英語で答える活動を取り入れる。ex)動作のある活動、実物を使用、歌…
③多すぎる新出単語で負担をかけない
n
“learn
a little, use a lot” を念頭に、文法に焦点を当てず、単語・句を学ぶ。新出単語の量も多くしない。
n
様々な活動で、同じ語句を学ぶ。ex) Body words
④理解可能なインプットを十分に与える
n
インプットが十分理解されたことを確認するために、絵、ジェスチャーなど様々な補助を用いる。教室内での教師の英語も、単純だが、極度に単純化されたり、非文法的な文章であってはいけない。同じ意味には同じ形式を用いる。
ex) Where are you from? Where do you come from?はどちらかに決める。
n
母語も初級者に助けにはなるが、母語の使い過ぎにはきをつけなければならない。
n
英英辞典を使用するには最低2000語の語彙が必要。
⑤
心地よく、安全で、協力的な教室環境を作る
n 学習者は不安であると積極性が下がるため、①~④の項目を考慮して、間違えを恐れない雰囲気を作る。
3. Activities and approaches for teaching and learning in a beginners’ course
3.1 役立つ語句・文を暗記する
n 役立つフレーズを覚えることで、簡単なコミュニケーションが成り立つ、文法の知識なしで言語正しく使用できる、Please say that again 等で会話を操作できる。その後の語や形式の学習を容易にする。
n 学習する文・句を決定する方法:生徒が言えるようになりたいと思うフレーズ・教師が生徒にとって必要だと考えるフレーズ、教材など
n ex) This is a pen.を最初に習ってもコミュニケーションは成り立たない(例p.24)
3.2 文形式を練習する
n 規則的に語を置き換えて他の文にする「置き換え表」(substitution tables)を用いる。(p.24参照)
n 一か所の置き換えから徐々に数を増やし、ランダムに指名、指名を速くする、文を消していくなど、活動に関心を持たせるようにする。
3.3 リスニングとスピーキングの指導 (p.26~)
n What is it? :物を描写する文を書く。他のものについて描写するためにどのように文を変化させるか示す。文の練習、伝達することによる結果がある、ペア・グループで活動できる、文を変更することで予測を難しくすることができる、などの特徴がある。
n Listening grids, survey : リスニング、調査をして表を埋める。(p.27 Table 2.1)
Interviewにも発展する
n Quizzes, puzzles:チーム制で解答できるよう競争する
n Listen and do: Total Physical Response (TPR)
n Bingo: ex) body part bingo 体の名前を教師が言い、単語と一致させる
n listening to pictures:絵を見て教師が描写し、生徒も続けて描写する。
n Information transfer:料理など過程があるものを描写し、異なる相手に繰り返し描写し伝える。
4. Techniques for early meaning-focused speaking
1文をグループ内で順番に作っていく活動。
n Descriptions: 描写、比較、説明など様々な形式の絵をグループ内で順番に描写していく。
n Hints: What is it の応用。各グループ、一つのもの(祖国の食べ物など)を描写する文を各自考え、他のグループは当てる。
n 3形式の質問
stage one questions: 絵、文に実際に明記されていることについてex) What is behind the house?
stage two questions: 実際に明記されていないが、事実を合わせて回答する質問 ex) What season is it?
How do you know it?
stage three questions: 生徒が想像力を使う質問 ex) What are these people thinking about?
n ask and move: 観光客と案内係。各案内係は異なった情報を持っている。
n twenty questions: あるものの名前を紙に書く。又は知らないものを見せる。yes/no questionsに答える。
n walk and talk: 2重の輪になって、質問、回答をして動いていく
n the same or different activity: ペアで別々の単語と定義、または定義と定義のリストをもち、同じものについてかどうか確認する。(p.32)
n odd one out: 文法、語彙、内容などについての間違い探しをする。ex) sung, broken, drank, rung
4.1 発音
大人の生徒にとって発音の直接的指導はより重要となる。音の区別、教師の口の動きに注目するなどの指導方法がある。発音の直接指導は授業内に短時間に行い、母国語と対象言語の発音の違いを認識させる。
5. Planning a listening and speaking programme for beginners
n 学習初期では、意味重視のリスニングのインプットを、物語など聞いて楽しむものと、返答が必要なもの(聞いて描く、情報交換など)との区別を明確にすべきである。
n 教室外でのインプットが十分でない場合は、リスニング・スピーキングクラスの4分の1は意味重視のリスニングに費やすべきである。
n リスニングは、多様な言語使用(フィクション、形式的、会話、)や題材を扱うべきである。
n 若い学習者:
週に数日朗読、読み聞かせ、グループでのリスニング活動。発音、語彙、文法も取り入れる。
n 大学準備クラス:
・ESL環境である場合は、形式的な講義や公演のリスニングを重視。
・ 公演者によるスピーチ、ニュース番組、難易度の高いトピック(地震、医療、保護など)についての受容的リスニングなど。
・ 全て英語で指導し、生徒が自由に語学練習室を使える環境にする。
n 釣り合いのとれた初期のスピーキングとリスニングの授業は以下の項目を含む。
・ 意味重視のインプット:教師との会話、聞いて活動、物語を聞くなど、様々な活動を取り入れる。
・ 意味重視のアウトプット:教師との会話、描写、質問活動など様々。
・ 言語重視の学習:発音、重要表現の暗記などを教師が指導。
・ 流暢さの向上:暗記した句を、標準な速さで読むことで繰り返し練習する。同じ物語文を速度を徐々に速くして聞く。暗記した句でロールプレーをする。数字の聞き取り。
※番号は便宜上付けたものである。
1.
The Importance of Pronunciation
・良い発音は、コミュニケーションや分かりやすさ(intelligibility)だけでなく、音韻ループ(Phonological Loop)にとっても有益である。
2.
The Place of Pronunciation Instruction
・本章では、発音を指導する言語重視の指導法を取り扱う。
3.
Goals
・どの英語を外国語学習者にとってのモデルとするべきかは、議論が続いてきた。
・Stevick (1978):発音とアイデンティティは強く関係している。
・Levis(2005):Nativeness principal:ネイティブスピーカーが学習者のゴールである。
Intelligibility principal:方言を容認し、理解をゴールとする。
・Jenkins(2002):分かりやすさ(intelligibility)が主要な基準となるべきである。
4.
Factors Affecting the Learning of Another Sound System
4.1 Age
・学習開始時期が・・・6歳前→訛りはなし、もしくは、ほとんどなし。
7歳から11歳→少し訛りがある。
12歳以降→ほとんどの場合訛りがある。
・学習開始時期が発音に影響を与える理由
◇説①Physical explanation:年齢に応じた脳内での物理的な変化が、新しい音声体系を学ぶのに影響する。
◇説②Intellectual explanation:既に母語の音声を学んでいるため、第2言語の音声の学習を混乱させる。そして年齢が上がるほど、母語の音声体系もより安定していく。
◇説③Psychological explanation:発音は個性(personality)の一部であり、年齢が上がるほどそれは変え難くなる。
・Stevick (1978)が考える3つの発音を妨げる要因
①いくつかの特徴を見落としている。②出来るが、わざと悪い発音をしている。③音を出すことが心配である。
4.2 The Learner’s First Language
・学習者の母語は他の言語の音韻システム(sound system)を学習するとき、大きな影響を持つ。教師は、学習者の母語の音韻システムを知ることにより、母語の影響について考慮することができる。
4.3 The Learner’s Development and Range of Styles
・文法の発達に中間言語があるように、音韻発達にも発達上の中間言語がある。よって、教師は学習者の発音の誤りを安定したものか、変わりつつあるものか判断すべきである。
・学習者の発音は、状況(formal/informal)によっても変化する。
4.4 The
Experience and Attitudes of the Learner
・英語圏に住んでいた期間、家庭での英語による会話の割合、英会話の練習量、学習者の知っている言語の数、ネイティブの先生の割合、モチベーションの種類、正確な発音に対する願望の強さ、模倣のスキル、外交的か内向的かなどが学習に影響する。
4.5 The Condition for Teaching and Learning
・学習者の発音を正す際には、無意味語や知らない語を使用したほうが良い。
・正しい発音のためには、音読は模倣よりも難しい。一方、スペルが発音規則をより効果的に示すこともある。
・早口言葉は、母語話者にとっても難しいため、外国語学習者にとっては本当に難しい。
・話し手の口の動きを見ることは、リスニングに重要な影響がある。
・母語の異なる学習者間でのコミュニケーションは、分かりやすさを促進するために良い方法である。
5.
Procedures and Techniques
5.1 Articulation of Individual Sounds
・発音の練習は、教師による観察、分析、選択に基づき、まずは異なる音の聴き分け、識別から始める。
5.2 Learning New Sounds: A Procedure
5.2.1
Necessary Information
(a)学習者の母語に習得しようとしている音(wanted sound)はあるか、どの音が近いか。
(b)習得しようとしている音の場所で、学習者はどのような発音をしているか。
(c)学習者が誤るのは、語頭か、真ん中か、語末か。
(d)習得しようとしている音と、そうでない音の違いは何か。
5.2.3
Hearing Sounds
◇Distinguishing sounds(音を聞き分ける活動):2つの音を教師が言う。2回とも同じ音(e.g. pa-pa)か、別々の音(e.g.pa-ba)かを学習者は答える。学習者は答えが分からないとき、同じ音であると判断しがちである。
◇Identifying sounds(音を識別する活動):教師は2つの単語を板書し、どちらか単語の隣に手の絵を書く。教師が言った単語が、手の絵が書かれている単語と同じ発音で始まっているかどうかを、学習者は答える。
◇Identifying sounds using pictures(絵を使って音を判断する活動):2つの絵を示し、教師が言った単語はどちらかを、学習者は答える。(e.g. ship-sheep)文の中に単語を入れて言うこともできる。(e.g. I see a ship. – It’s in the port.、I see a sheep. – It’s eating grass.)
・異なる音を聞き分けるときには、音のみ、もしくは、無意味語を提示するのが良い。学習者がよく知っている語は、注意が音以外にも注がれたり、元々の誤りが影響してより難しくなったりする。
・音を聞く活動では、学習者に目を閉じさせたり、教師が口を隠したりすることもできる。◇Don’t be tricked:示されている音を教師が発音しているかどうかを、学習者が判断する活動。
◇Keep up:少しだけ音の異なる単語を板書する。教師は、素早く単語を読み上げる。学習者は言った順番を書き留める。
◇Multiple-choice sounds:5つの単語を一つのグループとした単語のリストを配る。教師は、5つの単語の中から一つをいい、生徒は丸を付けていく。2順目には三角、3順目には四角、と指定することで、何度もその単語リストを使用することができる。
e.g. 1 heat hit eat hat it 2 can kin ken gone Kim
◇Triplets:教師は3つの音、もしくは単語を言う。学習者は、同じ音は何番目と何番目であったかを答える。 (e.g. fa pa pa – 2,3、fa pa fa – 1,3) 4語以上でもできるが、その場合には記憶力がより重要になってくる。
・Briere(1967)によると同じ音が続く方が、簡単である。Denham(1974)も順番が難易度に影響するとしているが、Briereとは若干異なる結果を示している。
◇Sound dictation:教師が無意味語、もしくは、未知語を言い、学習者はそれを書き取る。正しく書き取れれば、正しく聞き取れたと判断する。もしくは、まず母音に番号を付ける。そして教師が単語を読みあげ、その単語に含まれていた母音の番号を生徒は答える。同じ子音を用いることで難易度を下げることが出来る。
◇Pronouncing to hear(聞くために発音してみる活動):教師が舌の位置を示すことで補助したりしながら、学習者は音を発音してみようとする。
・新しい単語を発音することで、学習者の正しく聞く能力が向上するという考えに基づく。
5.2.4
Producing Sounds
◇Repeating sounds:教師は新しい語や難しい語を言う。学習者はそれを聞き、リピートする。学習者が発音できるようになったら、文字や絵、実物を示し発音させることができる。
・Locke(1970)によると、2回新しい語の発音を真似ても、ほとんど向上は見られない。よって、リピートは短時間で出来、便利というだけで、他の発音指導が必要である。
◇Slurring:舌などをある形から別の形へとゆっくり動かし、学習者にもそれを真似させる。動きを途中で止めることで習得したい音が発音される。
◇Bracketing:2つの音を交互に発音し、真似させる。2つの音の間の音を発音させる。
・SlurringとBracketingは、難しい母音の練習に使うことができる。
◇Diagrams for pronunciation:舌などの口の絵を示す。口の絵と共に、教師の手を舌として示すこともできる。
◇Testing the teacher:聞き分ける活動の教師と学習者の役割を入れ替える。
◇Using the written forms:子音結合から始まる単語を沢山提示し、それらを元に同じ子音結合から始まるグループに分けさせる。この活動はスペルと発音の関係を示すこともできる。その後、無意味語を教師が発音し、それが英語として有りうる発音かどうかを判断させる活動も出来る。
5.2.5 Correcting Pronunciation Mistakes
◇発音を訂正する方法
・学習者自身が自ら発音を直すまで、教師が普通の強勢とイントネーションで単語をリピートする。
・学習者が誤った箇所に強勢を置いたり、長く言ったりしながら、単語をリピートする。
・教師は誤った発音と正しい発音を比較する。(e.g. “Not lice but rice.”)
・教師は単語を板書し、誤った箇所に下線を引く。そして正しく発音してみせる。
・“No”といい、補助なしに誤りを見つけさせる。教師は誤った箇所で机を優しくたたくことでヒントを与えることもできる。これは、学習者が正しい発音を出来るにもかかわらず、忘れたときに用いることができる。
5.3 Stress and Intonation
・言語はstress-timed languageとsyllable-timed languageに分けることができる。そして、syllable-timed languageを母語とする学習者が英語を学ぶ際には、話のリズムパターンの習得に手助けが必要である。
5.4 Teaching Word Stress
◇単語の強勢の指導法
・教師が、強勢のある箇所では強く、そうでない箇所では軽く手を叩く。
・教師が、強勢のある箇所は長く発音する。
・学習者が単語を言うとき、教師が強勢の置かれる場所でジェスチャーをする。
・教師が文を言い、強勢を注目したい単語の前で止める。その単語の強勢を手を叩いて伝え、リズムと文脈から次に来る語を考えさせる。
・学習者は単語リストを配布される。教師はそれを読みあげ、学習者は強勢の置かれている音節に下線を引く。
・学習者は単語リストを渡され、それを強勢の置かれるパターン別に分類する。それぞれのパターンの例を教師は示すことができる。
5.5 Teaching Sentence Stress
◇文の強勢の指導法
・教師が机を叩き、リズムを示す。
・英語のリズムを説明し、リピート用のモデルを提示する。
・2つの強勢がある文をリピートさせ、強勢の数は変えずに文を長くしていく。
e.g. The boy’s in the house. ・・・> The little boy’s not in the old house.
・詩の音読も英語のリズムの学習に役立つ。
5.6 Teaching Intonation
◇イントネーションの指導法
・学習者が教師を真似る。
・学習者はイントネーションの変化に沿ったジェスチャーをする。
・正しいイントネーションで、文の最後の単語から言っていく。
・イントネーションの図を示す。
6.
Fitting Pronunciation into a Course
◇発音指導の形態
1.全授業時間の中で、発音に焦点を当てた時間を定期的に設ける。音を聞き分ける活動、判断する活動、リピート(repetition drills)、観察されたスピーキング活動(monitored speaking activities)などを含む。
2.発音は時々焦点が当てられる。
3.発音の誤りが見られたときに指導する。他の人が何か別のことをしている間に、個別、もしくは、グループ単位で指導する。
4.発音に焦点が当てられた指導はしない。意味重視のスピーキング活動を行う。
・学習者は自然な会話でも練習した発音を使用できるようになる必要がある。(参:Table 5.1)
・Stevick(1978)は、学習者の気持ちに応じた3つのアプローチを示している。
1.教師はほとんど話さず、学習者自身で発音の基準を見つけさせる。
2.学習者の見えない場所、しかし、学習者の個人空間のなかにある場所で発音する。
3.まず学習者が発音し、その後、それが正しいか否かに関わらず教師が正しく発音する。
・分かりやすい発音を学習者に示すためには、split information activitiesなどによりコミュニケーションの難しい状況を与えるのが効果的である。
7.
Monitoring Pronunciation
◇学習者の発音のテスト方法
・学習者があまり多くないときには、一つのpassageを録音させる。
・minimal pairの文が書かれたプリントを配布し、生徒はそれぞれの文でどちらか一方に丸を付ける。生徒は一人ひとり、丸をつけた方の文を読み、教師は生徒がどちらを言っていたかを記録する。生徒のプリントと教師のメモを比較し、評価する。
・minimal pairに基づいた10パターンのプリントが作られ、ランダムに配布される。生徒は、プリントの英文を読みあげ、教師はminimal pairのどちらが発音されたかを聞き取る。その後生徒がプリントに書いてある答えを読みあげる。
|
プリントA 1. She couldn’t be heard in class. 2. He guards his shin carefully. 3. Give him his tie back. 答え)1a, 2b, 3a |
プリントB 1. She couldn’t be heard in class. 2. He guards his chin carefully. 3. Give him his tie back. 答え)1a, 2a, 3a |
・流暢さを向上させる活動は、発音の正確性向上にも良い影響があるかもしれないが、まだ研究の余地がある。
Chapter7 Learning through Pushed Output (pp.115-130)
■学習者は、十分な言語体系の知識を持つまでスピーキングは奨励されるべきではないと言われているが、学習者が話すことが強いられないと、知識は生じないと述べている研究者もいる。
・学習者はスピーキングよりもリスニングに慣れている。
・強制的アウトプット(pushed output)をすることで言語産出における文法の重要さに気付く。
Pushing
Output
・学習者にアウトプットさせるようなスピーキングタスクを計画する際、考慮すべき要素は「トピック」「テキストタイプ」「パフォーマンス状況」の3つ。
◆トピック(Topic)
・学習者はトピックの範囲内で話すべきである。
・語彙にもっとも影響する。
・トピック内容に詳しいかそうでないかというような、背景知識の量とも関連がある。
◆テキストタイプ(Text Type)
1. involved interaction vs. monologue
…一人が話しているのか、相互行為なのか?
2. colloquial speech vs. formal speech
3. short turn vs. long turn
…会話を短くしているのか、より長く連続したスピーチをする機会があるのか?
4. interactional vs. transactional speech
…スピーキングのゴールは親密関係を築くためなのか、重要な情報を知らせるためなのか?(Brown,1981)
5. narrative vs. non-narrative
◆パフォーマンス状況(Performance Conditions)
・学習者がスピーキングタスクを行うとき、様々な状況下でタスクを行うことが出来る。
①Planning
・タスクが行われる前にタスクを準備すること。トピックについて考えたり、言うことを
準備したり、あらかじめメモをとることなどに関連する。
・planningは言語産出の手助けとなる。
・10分間のplanning timeが良い結果をもたらすのには十分という調査結果もある。
・タスクの準備をさせるような活動は、以下に挙げられる。
◇Retelling
・受容言語知識を生産的使用に持ち込む最も効果的な方法の一つ。
・書き言葉のテキストの再話や聞いたことの再話。(pp.118参照)
・下線の引かれた語彙は学習者にとって未知であるが、インプットをすることでこの項目を理解させ、これを生産的に使用させることが出来る。
・グループのメンバーでタスクの準備を行い、リハーサルしたり、割り当てられたトピックについて調査したりすることが可能。
◇Class judgment
・タスクの準備が不可欠な活動。
・2人の学習者がクイズの参加者として選ばれ、テキストが与えられる。クラスの生徒たちも同じものを持ち、2人が質問される内容も知っている。クイズの参加者は口頭でテキストの内容について質問され、残りの生徒たちはその答えが正しいかどうかをメモに書く。(Picken, 1988)
◇Ask and answer
・ペアで活動する。
・片方がテキストを持ち、もう片方がテキストに関連した質問を持っている。そして片方がもう片方にテキストについて知っていることを言うように質問をしていく。
・何回か練習をし、最終的にはクラスの前で行う。
②Time pressure
・On-line planning
考えをスピーチにするために、話している間に注意を向けるもの。正確さ(accuracy)に良い影響をもたらす傾向がある。
・Pre-task planning
Prepared taskのこと。スピーキングタスクを行うのに十分な時間を学習者に与えることで、明示的文法知識と暗示的文法知識の両方にアクセスさせることが可能となり、産出されたアウトプットの質を向上させることにつながる。
③Amount of Support
・支持されたタスクは学習者に最も良い状況下で産出させることが出来る。
→理解や思いやりのある、協力的な聞き手の存在が必要。
1.聞き手を協力的なストラテジーで訓練させること
“you said…”ストラテジーや、ask and answerなどが効果的。また、3人で行う場合は1人が話し手、もう1人が聞き手、そしてもう1人がチェックリストを使用して、聞き手のモニター役になることが出来る。(チェックリストはpp.119下部参照)
2.聞き手にスピーキングの難しさを経験させるような機会を与え、その難しさを反映させること
④Standard Performance
・上手に話さなければならないという学習者のプレッシャーは、公共の前で話さなければならないときや、自身のパフォーマンスに対して判断がなされるというようなときに増加する。
・他者とのスピーキングは協力的であり、要求されている。
Informal
Speaking
・情報を伝えることが親密な関係を作り上げることほど重要ではない場合に関連する。
・Brown(1978)はinformal speakingを相互行為スピーキング(interactional speaking)とした。相互行為スピーキングは以下のように支持される。
1.学習者は会話が続くように手助けする会話のストラテジーが教えられる。
・Q->SA+EI
→質問(Question)は短い答え(Short Answer)によってフォローされ、答えについて余分な情報(Extra Information)か加えられる。
2.会話において協力的なパートナーを持つことでスピーキングをより簡単なものにすることができる。
3.タスクの繰り返し
・最初はスピーキングが難しくても、繰り返すことによって簡単なものになる。
例:retelling, pass and talk
◇Pass and Talk
・絵やクラスについてなどが書いてあるカードの説明をする。または、グループ内の人
について言ったり、最近のニュースについて述べたりする。
・それぞれがタスクを終えた後、カードをグループ内で回し、繰り返す。
4.Informal speakingは準備されるべき。
5.話し言葉は書き言葉よりも多くの、2語以上からなる単位を使用する。
→我々のスピーキングのほとんどはinformal speakingになりがちである。
Formal
Speaking
・planning, time pressure, support, standard of performanceのすべての状況下において影響される。
・formal speakingは内容の操作、聴衆が受け身であることに気付くこと、注意に焦点を当てることを必要とする。
・L1の研究において、長く話すためのスキルを発達させる方法(Brown, Anderson, Shillcock and Yule, 1984)
1.聞き手の観点からタスクを経験すべき。
2.複雑さが徐々に増しているようなタスクを通して活動する機会を持つべき。
The
Nature of Formal Speaking
・いくつかの重要なポイントがある。
1.処理的である(transactional):情報を伝えるということが目的。
2.長いターンを持つ
3.書き言葉により影響される:メモからのスピーキングや、専門的な語彙に関連する。
4.スピーキングは、学習者の明確で慎重な「注意深い」スタイルで、産出をモニターするような機会を伴ってなされる。
5.典型的な言語使用の一部ではないスキルとして教える必要がある。
Teaching
Formal Speaking
・話し手に興味のある話題が話されるべきである。
・formal speakingは長いターンをとるので、多くのNSはそれを難しく感じるが、学習者は長いターンを構成する方法に気付くべきである。ターンの計画には様々な方法がある。
1.話し手は長いターンを構成する効果的な方法を発表したり見つけたりするだろう考えを知ることが出来る。
2.考えを組織する標準的な修辞の枠組みを使用することが出来る。
3.トピックタイプのような標準的情報の枠組みを使用することが出来る。
4.グループでのplanningは話し手を手助けする際に有用。例:moderation
◇Moderation
・教師は話し合うトピックを紙に書き、学習者はそのトピックについての考えを小さな
紙に書く。それを集めて、教師は大きな紙にまとめる。学習者はその意見を明らかに
するために話し合う。もし反対だったら”Objection!”と言い、意義は異なる色の紙に書
かれて考えの横に置かれる。それからそれぞれの考えについて考え、自分が最も重要
だと思う見出しにステッカーを貼る。
・学習者はメモの準備をすることやメモから話すということを訓練すべき。
◇pyramid procedure(Jordan, 1990)
・話すためのメモを学習者が一人で準備すること。
・メモを使って話し、フィードバックをもらう。
・3,4人の小グループで話をする。最終的に短いメモだけでクラス全体に対して話しを
する。
◇serials activity
・学習者はグループで活動し、数日にわたって話の準備をする。
・グループごとに異なる話を準備し、他のグループは話が面白かったか、上手く発表で
きていたかなどについて返答する。(Hirvela, 1987)
・話は、絵や、個人についての話、神話などから選ぶことが出来る。
・Table7.1参照。
A
Process Approach to Formal Speaking
・ゴールを作ること、アイデアを集めること、スピーキングメモを作ること、話をしたりモニターしたりすることなどにタスクをわけることが出来る。
・話し手は聴衆の一人になるという経験をすることで、聴衆から質問やフィードバックをもらうことで、そして話の中で聴衆の反応を見ることで聴衆の意識を知ることができる。
・Table 7.2参照
・教室内で、互いにタスクを行うことは有用であり、聞き手と話し手の両方の役割を経験することができる。
◇Triads
・AとBが会話をし、Cが審判を行う。
・1つのトピックについてAが短い話を2つか3つし、Bがパラフレーズする。それをA
とCが注意深く聞き、間違っているようだったら訂正をする。
・役割を交替して行う。
・より良い発表を行うために、発表するものを集めたり、推敲したりするためにグループワークを行う。
◇Brainstorming
・アイデアを出し合い、なるべく多くの考えを得るということ。利点は、様々な考えを
集めることが出来るということである。
・より多くの焦点化された情報を集めるために、情報スキーマや自己質問票などを使用
する。
Guidelines
for Presenting a Formal Talk
1.3つか4つの重要なものにメッセージを絞る。
2.「シンプルな」アウトラインで構成する。
3.3つか4つの焦点の変化があるべき:全体の話が、話し手→聞き手という構成にすべきではないということを意味する。
(a)話し手は聞き手に対して話す。
(b)聞き手は話し手に質問する。
(c)聞き手はペアになって話をする。
(d)聞き手の一人は残りの聞き手に話しかける。
(e)聞き手はハンドアウトを見て、短い映像やデモンストレーションを見る。
4.聞き手は質問をする、フィードバックを与える、タスクについて答えることで話に関与すべきである。
Monitoring
Formal Talks
・フォーマルスピーキングタスクの過程の区別(Table 7.2)はフィードバックを与えたり、モニタリングしたりすることに対して有用。フォーマルトークを聞くとき、教師と学習者の両方が話し手の強みと、弱点を分析的に見ることが出来る。
①Goals and Audience
・適切な言葉遣い、発表の速度などを通して聞き手の意識を示しているか。
・話し手のゴールは明確か。
②Ideas
・話していることについて十分に関連しているか。
・話し手は十分な量の情報を発表しようとしているか。
③Organization
・話は十分に構成されているか。
・話の構成は聞き手にとって明確なものであるか。
④Notes
・話し手は聞き手に話しかけているか。
⑤Presentation
・話しぶりは流暢なものか。
・聞き手の意識を保っているか。
・焦点の変化をしているか。
◆他の人と話すことは学習者にアウトプットをさせ、自身の知識におけるギャップに気付かせる。この章の多くがフォーマルスピーキングに焦点を当てていても、それはスピーキングを通して学ぶことの手助けをするバランスのとれたプログラムの一部にすぎない。
1.
The Nature of Fluency
◆流暢さはリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4つのスキルにおいて特徴づけられる。
(1) 学習者は、意味に焦点を当てた活動に参加し、そして会話の流れを止めることな
くある程度のスピードと精神的な気楽さをもってその活動を行っているときに、
流暢さを発揮する。
(2) 流暢な言語使用は学習者の多くの注意と努力を必要としない。
(3) 流暢さは技術である。流暢さは言語知識の質に依存し、その能力の向上には知識
の更なる構築が必要とされるが、本質的には、すでに知っていることを最大限活
用することである。
以上の3つ、message-focused activity, easy
tasks, performance at a high levelが流暢さの上達のためにデザインされた活動の主な特徴でもある。
2.
Fluency and Accuracy
◆流暢さと正確さの関係
・Nation (1989a), Arevart & Nation (1991)
流暢さを向上させるための活動が、結果として誤りを減らし文法的な複雑さを生む。
・Skehen (1998)
流暢さは速さや口ごもりの数によって測ることができる。一方で正確さは間違いの数、複雑さは従属節のようなより複雑な構造の存在によって評価される。
3.
Developing Fluency
◆流暢さを上達させる条件
(1) 意味重視な活動。学習者の意識がメッセージの意味にあり、’’生の時間’’のプレッ
シャーと意味重視のコミュニケーションの要求に晒されている。
(2) 言語項目が学習者の経験内にある活動をする。’’experience’’ task
例) 馴染みのあるトピックや知っている語彙や構造を利用した談話
(3) 学習者が通常のレベルよりも高いレベルで言語運用ができるようにサポートした
り励ましたりする状況。
⇒流暢さの上達が目標である活動では、学習者は早く話したり理解し、口ごもりを少な
くしなければならない。時間のプレッシャーを利用して、高いレベルでの運用を意識
的に後押しする
4.
Designing Fluency Activities
上記の3つの条件を最大限に活かした、流暢さのための活動をどのように作り上げればいいのか
4.1 4/3/2
Maurice (1983)
ペアになり、4分間話し、もう片方が聞く。交換して3分間で同じ内容を話す。再び交換
して2分間で話す。流暢さの観点からこの活動には3つの重要な特徴がある。
(1) 学習者に多くの量を話すことを促進する。
(2) 要求が制限されている。時間制限があること、繰り返しが学習者の注意をメッセ
ージに向けさせていること。流暢さの向上が達成すべき目標であること。
(3) 学習者は発話を繰り返す機会を与えられることによって、またメッセージを伝え
る時間を短くすることで、高いレベルに達するための手助けを受けることになる。
4.2 Easy
Tasks
活動で必要とされる言語、思考、会話のすべてを学習者が以前に経験したものであれば、学習者は流暢さを向上させることができる。例えば、スピーキング活動においては、自分自身に関するトピックを与え、自分で書いたものを基にしてスピーキングをさせる。
4.3 Message
Focus
明確な成果があると、学習者は成果を得ようとして言語をしようするので意味重視を促進する。例えば4/3/2の活動では、明確な成果はないが、話し手は話しているという強い自覚があるので、意味に重点を置いたものとなる。
4.4 Time
Pressure
4/3/2にもあったように、時間制限を設けることによって学習者を高いレベルに引き上げるよう奨励する。same or differentやfind
the differenceにも応用できる。学習者はあるタスクにかかった時間を保持し、その記録を越えようとする。
4.5 Planning
and Preparation
◆より高いレベルに到達する方法は、準備をして活動の質を高めることである。
・Cookes(1989)
LEGOの組み立て方や地図の完成させ方を説明するというタスクを課した。10分間
の準備時間を与えられた学習者は、準備していないものに比べて、長く、文法的に
複雑な発話を行った。
・スピーキングやリスニングをする前の準備の活動の例としてブレインストーミングや
トピックについて事前に読み込むというものがある。
4.6 Repetition
繰り返すことは流暢さを高める上で確実な方法と言える。4/3/2活動のように、ペアを変えて繰り返し発話することが大切である。それによって発話者は、聞き手の関心を保つために発話内容を変えることはしなくてよいので、意味に焦点を当てた活動が可能になる。
5.
Fitting Fluency into a Course
◆新しい言語項目を学習することと流暢さの向上という2つの目標
・第二言語が教室外で使われることがないのであれば、授業の1/4は流暢さを向上させるための活動に時間を割くことは重要である。
Brumfit (1985):初めは授業の1/3を流暢さのための活動に使い、徐々にその時間を増
やしていくことが良い。
・毎回の授業に流暢さを向上させる活動を取り入れ、かつその授業で教える新しい言語項目を利用するならば、流暢さの密度は小さくなってしまう。
⇒リスニング教材については、学習者が99%の言葉を知っていること
数日前か、もしくは数週間前に習ったものを活動に取り入れること
流暢さの活動のために多くの時間を割くこと が重要である。
◆他のスキルとの繋がり
・流暢さを向上させることには、リスニング、スピーキング、ライティング、リーディングなどの様々な技術がリンクしている。そのため、学習のはじめに行う活動は、あとに行う活動に大きな影響を与える。そしてそれは高いレベルに達することを可能にする。
・リスニングやスピーキングなどのリンクしている様々な活動の最終目的が流暢さであるならば、次の事柄を確認することが有益である。
(1)単元のはじめに行う活動が、あとに行う活動に役立つように準備されているか。流
暢さが最終目的であるならば、単元のはじめに使う言語、思考、テキストは学習者の既知のものを使うべきである。
(2)単元の最終部は、流暢さを学ぶという最終目標を達成しているかどうか
◆他に確認すべき事項
(1)タスクを行う前に必須の項目やスキルを学ぶ必要性
(2)言語の様々な面を練習すること、集中的な言語使用
(3)教室外で使うことを想定した活動を行うこと
(4)学習を助けるために語彙や文法を繰り返す機会を与えること
(5)実用的であること
6.
Developing Fluency in
Listening and Speaking
◆流暢さの上達への3つのアプローチ
(1) the well-beaten path approach:同じ教材を繰り返し練習する
(2) the richness approach:知っている情報から繋がりを作る
(3) the well-ordered system approach
:上の2つのアプローチの結果。自身で言語システムを制御したり、効率的
に、良く繋がっている情報を使う。
7.
Techniques for Developing
Fluency in Listening
◆リスニングの流暢さを向上させるために必要なテクニック
(1)意味に焦点を当てた活動を含んでいる。例えば、面白い話を聞いたり、パズルやクイ
ズなどの明確なコミュニケーションの成果がある活動を含む。
(2)学習者がすでによく知っているような言語の項目やトピック、経験知識に非常に頼っ
ているという点で、ごく限られた要求を学習者に向ける。
(3)そのテクニックは、意味中心の反復を通して、インプットの速度や予測の機会、前出
の背景知識の使用などを増やしながら、レベルの高い出来栄えに達するよう促進する
ものである。
◆Top-down processingとBottom-up
processing
・流暢さのタスクはtop-down processingよりである。なぜなら学習者に言語形式で頭を悩ませることのないスピードで言語運用させるからだ。
・top-down processingは学習者にとってトピックや構造に馴染みがあるとき、注意が特にメッセージに向けられているとき、言葉の細部に意識が向かないときにリスニングを促進する。
・Bottom-up processingは情報の主な資源がテキスト自体だったり、聞き手が準備や以前の経験を生かせないときに起こる。
7.1
Name it
教師が何かを描写している文を話し、学習者が答える活動。例えば、「歯をきれいにするためにそれを使います」と言ったら学習者は描写された名前(ここでは「歯ブラシ」)を言ったり書いたり、黒板に書かれた語群の中から選んだりして解答する。学習者が日常的に馴染みのあるものを使う。
7.2
Listening to questions
教師が学習者に質問をし、それに答える活動。質問は絵をもとにしても良いし、読み取りの文をもとにしても良いし、一般的な知識でもよい。True/ falseでもよい。
7.3
Listening corner
教師は学習者がすでに済ませたライティングの口語版のテープを作る。ライティングは個人的にやっても良いし、グループでも良い。代わりに以前読んだテキストの音声でも良い。
7.4
Listening to stories
リーディングはできるがリスニングが苦手な学習者にあった活動である。教師は面白い話を選んで学習者に毎時間聞かせる。学習者はただ聞いて楽しむ。教師は読んでいるときに黒板に聞いただけではわからないであろう単語を書いていく。できるだけそのような単語がないような話を選んだほうが良い。初めのうちは繰り返したり、ゆっくり読むが、慣れてきたら繰返しを少なくし、スピードも上げていく。
7.5
Listen again
学習者が以前聞いた話を、異なる単語を使って教師が話す。
7.6
Listening while reading
テキストを見ながら聞く。聞く前に学習者は、そのテキストや語彙などを確認する時間を持てる。
7.7
Peer talks
学習者はクラスや小さなグループで発表する話の準備をする。これらの話は言語使用のレベルが聞き手にあっているので、リスニングスキルを向上させる。成人の学習者であれば、トピックを仕事や技術についてでも良い。若い学習者であれば、新聞記事や世間話でもいいだろう。Farid (1978)は話が終わった後に話し手に質問し、互いに理解を深めることを提案している。
7.8
Interview
インタビューを録音したものを教材に使うことは興味深い。
・Simpson (1981):ノンネイティブがネイティブにインタビューする
(1)ノンネイティブが質問の種類や得る情報量をコントロールできる
(2)ネイティブはノンネイティブに向かって話すので、聞きやすい。
聞いている間に学習者は表を埋めたり、文を完成させる。
7.9
Predicting
ある話について情報をいくつか与えられ、その後何が起きるかを予想する。予想した後は、話を聞いて予想が合っているかどうか確かめる。与えられる情報は、不完全な文章や統計の表、話の題名、話の前置きでも良い。
8.
Techniques for Developing
Fluency in Speaking
8.1
4/3/2
メッセージに焦点を当てる、産出の量、学習者がトピックや言語使用をコントロールする、繰り返し、時間の圧力という特徴を兼ね備えている。
8.2
The best recording
学習者は以前の経験者、何らかの絵の描写について話し、それをテープに吹き込む。改善できそうなところに注意しながらテープを聞く。再度、その話を録音する。学習者は満足するまでこの作業を続ける。このテクニックは計画を立てることと繰り返しを促す。
8.3
Ask and answer (Simcock,1993)
学習者はより理解するためにテキストを読む。ペアで作業し、教師が準備してきた質問のリストから、1人の学習者がテキストについてもう1人に質問する。質問の答えは読んだテキストの要点である。何回か練習したら、クラスの前で発表する。この活動の目的は学習者がクラスの前で高いレベルの流暢さで質問と応答を行うことである。
8.4
Rehearsed talks
学習者はピラミッド型の手順を使う。
個人で話す準備→ペアで練習→小さなグループで練習し→クラスの前で発表する
9.
Monitoring Fluency Tasks
9.1
Examining the Context of the Material
◆experience tasksを使用するとき、タスクのどの部分が学習者の経験内なのか、どの部分が学習目標として焦点を当てられているかチェックする方法があると効果的である。
◆Language item goals, Idea or content goals, Skill goals, Text or discourse goalsの4つがその学習目標として使われるが、どんなタスクもこれらの目標のうち1つを持っているべきで、他の3つは学習者の経験内であることが望ましい。
◆タスクをチェックするときの質問
(1) そのタスクの学習目標は何か
(2) タスクの他の3つの面は学習者の経験内であるか
9.2
Examining the Teaching Material
Table
9.1 Fluency Checklists
◆流暢さの活動は学習者がタスクを扱いながら流暢さが向上しているかを確認するためにも使うことができる。その流暢さの変化を測る指標は、Lennon (1990)によると話す速さとポーズであるが、教師が主観的な判断で評価していることが多い。
◆教師が授業ごとに新しい教材を用意する必要があると感じているので、流暢さは疎かにしがちな要素である。